「都会の喧騒から離れて、自然の中で働きたい」「食に関わる仕事で社会に貢献したい」――そんな思いから、養鶏場の仕事に興味を持つ方は少なくありません。しかし、インターネットで検索すると「養鶏場 仕事 きつい」といったネガティブな情報も目にし、漠然とした不安を感じているのではないでしょうか?
もしかしたらあなたは、デスクワーク中心の仕事に閉塞感を覚え、もっと体を動かす仕事や、自分の働きが目に見える形で成果になる仕事を探しているかもしれません。でも、本当にその仕事が自分に合っているのか、想像以上に「きつい」部分があるのではないか、と心配になりますよね。
この記事では、養鶏場の仕事の「きつさ」を包み隠さずお伝えするとともに、それを乗り越えるための具体的なヒント、そして何よりこの仕事でしか得られない「やりがい」や「魅力」についても深く掘り下げていきます。単なるネガティブな情報に惑わされることなく、リアルな情報を知ることで、あなたが後悔のないキャリア選択をするための一助となれば幸いです。
「きつい」は本当?養鶏場の仕事で特に大変な5つのこと
「養鶏場の仕事はきつい」と言われるのには、明確な理由があります。ここでは、特に多くの人が大変だと感じる5つの側面を具体的に見ていきましょう。
1. 体力的な負担が想像以上に大きい
養鶏場の仕事は、基本的に肉体労働です。
* 重労働の連続: 鶏の飼料は袋で運ぶことが多く、1袋あたり20kg以上になることも珍しくありません。それを毎日何十袋も運んだり、鶏舎の清掃で大量の糞尿をかき出したりと、重労働が続きます。
* 早朝からの作業: 鶏の活動サイクルに合わせて、早朝(日の出前後)からの作業が一般的です。夏場は特に暑くなる前に作業を終えるため、午前3時や4時に出勤することもあります。
* 中腰やしゃがみ姿勢: 卵の回収や鶏の健康チェック、移動作業など、かがんだり中腰になったりする作業が多く、腰や膝への負担が大きいです。
特に、普段からデスクワークが多い方や運動習慣がない方は、最初のうちは全身が筋肉痛になり、想像以上の疲労を感じるかもしれません。
2. 衛生面と独特の「臭い」に慣れるまで一苦労
養鶏場は生き物を飼育する場所であるため、独特の環境があります。
* 糞尿の臭い: 鶏舎内には常に鶏の糞尿があり、特に夏場や湿度が高い時期は強烈なアンモニア臭が立ち込めます。この臭いに慣れるまでには時間がかかり、人によっては吐き気を感じることもあります。
* 粉塵と羽毛: 鶏舎内は乾燥すると粉塵や鶏の羽毛が舞いやすく、アレルギー体質の方や呼吸器が弱い方は注意が必要です。マスクは必須アイテムとなります。
* 虫の発生: 鶏舎にはハエなどの虫が発生しやすく、特に夏場は大量発生することもあります。
最初は戸惑うかもしれませんが、慣れてしまえば気にならなくなる人も多いです。しかし、潔癖症の方や臭いに敏感な方は、この点が大きなハードルとなるでしょう。
3. 命を扱う精神的な負担と責任
養鶏は、文字通り「命」を扱う仕事です。
* 病気や死への直面: 毎日多くの鶏と接する中で、病気になったり、命を落としてしまう鶏に直面することは避けられません。時には、弱っている鶏を安楽死させる判断を求められることもあります。
* 大規模殺処分のリスク: 鶏インフルエンザなどの伝染病が発生した場合、感染拡大を防ぐために数万羽、数十万羽といった規模で鶏を殺処分しなければならない事態に直面することもあります。これは非常に精神的な負担が大きく、トラウマになる人もいます。
* 食の安全への責任: 毎日口にする卵を生産しているという重い責任感も伴います。品質管理や衛生管理には常に細心の注意を払う必要があります。
命を扱う仕事だからこそ得られる喜びがある一方で、その裏側にある厳しさも理解しておく必要があります。
4. 年中無休の管理体制と時間的な制約
鶏は毎日卵を産み、毎日成長します。そのため、養鶏場に休みはありません。
* 早朝勤務と休日出勤: 卵の回収や飼料供給は日々のルーティンであり、早朝からの作業は必須です。また、鶏舎の清掃や設備のメンテナンスなど、休日も出勤が必要な場合があります。
* 年末年始やお盆も関係なし: 鶏に休みはないため、世間がお休みモードの時期でも、作業は通常通り行われます。家族や友人と予定が合わせにくいと感じることもあるかもしれません。
* 長時間労働の可能性: 規模や人手によっては、一人当たりの作業量が多くなり、長時間労働になりやすい傾向もあります。
規則正しい生活リズムが身につくというメリットもありますが、プライベートとのバランスを取る工夫が必要になります。
5. 人間関係と閉鎖的な環境
養鶏場の多くは地方にあり、比較的少人数のスタッフで運営されていることが多いです。
* 少人数ゆえの人間関係: 限られた人数で毎日顔を合わせるため、人間関係が密になりやすいです。良好な関係が築ければ良いですが、一度こじれると居心地が悪くなる可能性もあります。
* 閉鎖的な環境: 都市部から離れた場所に位置することが多いため、仕事とプライベートの切り替えが難しいと感じる人もいるかもしれません。
* 地方ならではのコミュニティ: 地方移住を伴う場合、地域コミュニティへの適応も必要になります。
実際にあった「きつかった」体験談
ある養鶏場で働き始めたばかりのAさん(20代男性)は、初日に飼料の袋を運ぶ作業で腰を痛めそうになったと言います。「たかが鶏の餌、と思っていたら、想像以上に重くて。一日中中腰で卵を回収していたら、腰が悲鳴を上げて、夜は湿布だらけでしたね。」
また、別のBさん(30代女性)は、鶏舎の独特の臭いに慣れるまでが大変だったと語ります。「最初はマスク越しでもツンとくる臭いで、正直『無理かも』と思いました。でも、数週間で不思議と慣れて、今では気にならなくなりましたけどね。」
きついだけじゃない!養鶏場の仕事で得られる3つの大きなやりがい
確かに養鶏場の仕事には厳しい側面がありますが、それ以上にこの仕事でしか味わえない深いやりがいや魅力があります。
1. 生命の尊さを実感できる喜びと達成感
養鶏の仕事は、まさに「命を育む」ことそのものです。
* 鶏の成長を見守る喜び: ヒナから育て、健康に成長していく鶏たちを見守る過程には、大きな喜びがあります。日々の世話を通じて、彼らが元気でいる姿を見るのは、何物にも代えがたい感動です。
* 命を支える責任と誇り: 毎日、数万羽の鶏の命を預かり、彼らが健康で快適に過ごせるよう管理することは、大きな責任を伴いますが、その分、無事に一日を終えた時の達成感は格別です。
* 新しい命の誕生: 孵卵から携わる養鶏場であれば、卵からヒナが孵る瞬間に立ち会うこともでき、生命の神秘と尊さを間近で感じられます。
2. 私たちの「食」を支える社会貢献性
卵は、私たちの食卓に欠かせない、身近で栄養価の高い食材です。
* 食のインフラを支える誇り: 自分が育てた鶏が産んだ卵が、スーパーに並び、多くの人々の食卓を支えているという実感は、大きなやりがいにつながります。日本の食料自給率向上にも貢献しているという誇りを持てます。
* 消費者の笑顔を想像できる: 毎日の食を通じて社会に貢献しているという手応えは、デスクワークではなかなか得られないものです。自分が作った卵で、誰かが美味しいオムライスやケーキを食べている姿を想像すると、自然と笑顔になれます。
3. 自然の中で働くことによる心身のリフレッシュ
養鶏場の多くは、豊かな自然に囲まれた場所にあります。
* 心身のリフレッシュ: 都会の喧騒から離れ、広々とした自然の中で働くことは、心身のリフレッシュにつながります。朝日に向かって作業を始め、夕焼けを見ながら一日を終える生活は、都会のストレスを忘れさせてくれるでしょう。
* 規則正しい生活リズム: 鶏のサイクルに合わせて早寝早起きが習慣になるため、健康的で規則正しい生活を送ることができます。体力がつき、心身ともに充実した日々を送れる人も多いです。
「きつい」を乗り越える!養鶏場で長く働くための3つのヒント
養鶏場の仕事の「きつさ」は、工夫次第で乗り越えることができます。長く、そして楽しく働くための具体的なヒントをご紹介します。
1. 体力づくりと自己管理を徹底する
肉体的な負担を軽減するためには、日頃からの準備と自己管理が重要です。
* 事前の体力づくり: 働き始める前から、ウォーキングや軽い筋力トレーニングなどで基礎体力をつけておきましょう。特に、腰や膝の筋肉を鍛えることがおすすめです。
* 適切な休憩と水分補給: 作業中はこまめに休憩を取り、夏場は熱中症対策として十分な水分補給を心がけましょう。
* 栄養バランスの取れた食事: 体を資本とする仕事なので、バランスの取れた食事でしっかり栄養を摂り、疲労回復を促すことが大切です。
2. 衛生管理と対策を徹底し、慣れる努力をする
臭いや粉塵は、対策である程度軽減できます。
* 防塵マスク・手袋の着用: 鶏舎内での作業時は、必ず防塵マスクと手袋を着用しましょう。アレルギーがある方は、高性能なマスクを選ぶと良いでしょう。
* 作業着の工夫: 作業着は汚れても良いもの、洗いやすいものを選び、必要に応じて防護服を着用することも検討しましょう。
* ポジティブな捉え方: 臭いや汚れは、生き物を育てる上で避けられないものと割り切り、慣れる努力をすることも大切です。「これも仕事の一部」と割り切ることで、精神的な負担を減らせます。
3. 心の持ち方とストレスマネジメントを工夫する
精神的な負担を軽減し、長く働き続けるためには、心のケアも重要です。
* 命への向き合い方: 命を扱う仕事であることを理解し、感謝の気持ちを持って鶏と接することが大切です。病気や死に直面した際は、一人で抱え込まず、同僚や先輩に相談しましょう。
* 仲間とのコミュニケーション: 少ない人数だからこそ、同僚との良好なコミュニケーションは重要です。互いに助け合い、悩みを共有できる関係性を築きましょう。
* 休日のリフレッシュ: オフの日は仕事から完全に離れ、自分の好きなことをして心身をリフレッシュしましょう。自然豊かな環境を活かして、ハイキングや釣りなどを楽しむのも良いでしょう。
養鶏場の仕事に向いている人・向いていない人の特徴
養鶏場の仕事には、向き不向きがあります。自分の適性を見極めるための参考にしてください。
向いている人
* 動物が好きで、命を大切にできる人: 鶏と毎日接するため、動物への愛情と、命を預かる責任感があることは必須です。
* 体力に自信があり、体を動かすことが好きな人: 重労働が多いため、体力があり、肉体労働を苦にしない人。
* 忍耐力があり、地道な作業を続けられる人: 毎日のルーティンワークが多く、地道な作業をコツコツと続けられる忍耐力が必要です。
* 責任感が強く、衛生管理を徹底できる人: 食の安全を支えるという意識を持ち、清潔さを保つ努力を惜しまない人。
* 規則正しい生活を好む人: 早朝勤務や休日の出勤があるため、規則正しい生活リズムを維持できる人。
向いていない人
* 潔癖症で、汚れや臭いが苦手な人: 鶏舎の環境にどうしても馴染めない可能性が高いです。
* 体力に自信がなく、肉体労働に抵抗がある人: 体力的な負担が大きいため、すぐに体を壊してしまう可能性があります。
* 動物が苦手、または命を扱うことに抵抗がある人: 鶏に触れることや、病気の鶏に直面することに強い抵抗がある場合は難しいでしょう。
* 単調な作業が苦手で、変化を求める人: 毎日同じ作業の繰り返しが多いため、刺激を求める人には向かないかもしれません。
* 不規則な生活を好む人: 早朝からの勤務や休日出勤があるため、自由な時間を重視する人にはストレスになる可能性があります。
未経験から養鶏の仕事に就くには?求人の探し方と注意点
「自分は向いているかも」と感じたら、次はいよいよ行動です。未経験から養鶏の仕事に就くためのステップと注意点をご紹介します。
1. 求人情報の見つけ方
* 農業専門の転職サイト: 「あぐりナビ」「農業ジョブ」など、農業・畜産業に特化した転職サイトは、多くの求人情報が集まっています。
* ハローワーク・地域の就職支援センター: 地元の養鶏場が求人を出していることがあります。地域に根差した情報が得られる可能性も。
* 自治体の移住支援窓口: 地方移住を検討している場合、各自治体が農業・畜産業への就職支援を行っていることがあります。
* 養鶏場のホームページ・SNS: 直接、興味のある養鶏場のホームページやSNSをチェックするのも有効です。
2. 就職前に確認すべきこと
* 研修制度の有無: 未経験者を受け入れている養鶏場であれば、OJT(実地研修)や座学研修の制度が整っているか確認しましょう。
* 給与・待遇、福利厚生: 肉体労働であるため、給与水準や社会保険、残業代、寮の有無などをしっかり確認しましょう。
* 職場の雰囲気と人間関係: 可能であれば、事前に職場見学や短期アルバイト、インターンシップなどを利用して、実際の職場の雰囲気や人間関係を肌で感じてみましょう。
* 将来性やキャリアパス: 経験を積んだ後のキャリアアップの可能性(管理職、独立など)についても質問してみると良いでしょう。
3. 面接でアピールすべきこと
* 熱意と学ぶ意欲: 未経験であっても、養鶏の仕事に対する強い熱意と、積極的に学び吸収していく姿勢をアピールしましょう。
* 体力への自信と健康状態: 体力が必要な仕事であるため、自身の健康状態や体力に自信があることを具体的に伝えると良いでしょう。
* 動物への愛情と責任感: 動物が好きであること、命を預かる仕事への責任感を明確に伝えましょう。
* 規則正しい生活への適応力: 早朝勤務や休日出勤への理解と、規則正しい生活を送れることを示しましょう。
まとめ:養鶏場の「きつい」は乗り越えられる「やりがい」と表裏一体
養鶏場の仕事は、確かに「きつい」側面が多くあります。肉体的な負担、独特の環境、命を扱う精神的なプレッシャーなど、初めて経験する方にとっては大きな壁に感じるかもしれません。
しかし、その「きつさ」の裏側には、生命を育む喜び、食を支える社会貢献性、そして自然の中で働くことによる心身のリフレッシュという、何物にも代えがたい「やりがい」と「魅力」が隠されています。これらの厳しさを理解し、適切な対策と心構えを持つことで、長く充実したキャリアを築くことが可能です。
もしあなたが今、養鶏の仕事に興味を持ちつつも不安を感じているなら、この記事がその不安を解消し、前向きな一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。
まずは、今回紹介した「きつい」側面を自分自身に問いかけ、どの程度受け入れられるか自己分析してみてください。そして、もし「それでもやってみたい!」という気持ちが湧いてきたなら、実際に養鶏場の見学に行ってみたり、短期のアルバイトを体験してみるなど、具体的なアクションを起こしてみましょう。あなたの新しい挑戦を応援しています!
養鶏場の仕事について、もっと詳しく知りたいことや、具体的な疑問があれば、ぜひコメントで教えてください。あなたの質問にお答えできるかもしれません。

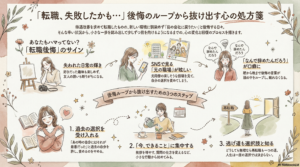
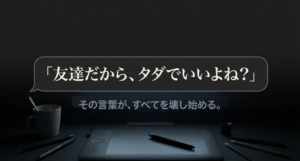






コメント