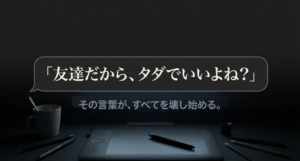美咲は、今日もアラームが鳴る前に目を覚ました。正確には、鳴る前から胸のざわつきで目が覚めてしまうのだ。3年目、プリセプター。その肩書きが、いつの間にか重い鎖のように美咲の心を締め付けていた。
「また今日が始まる…」
鉛のような倦怠感が全身を覆い、ベッドから起き上がるたび、鏡に映る自分の顔は、目の下のクマが濃く、以前のような明るさは失われていた。病棟に着けば、新人のAさんが待っている。指導は美咲の重要な役割だ。しかし、Aさんの小さなミスを見つけるたび、美咲の心は板挟みになる。「ここで厳しく言わなければ、Aさんの成長の妨げになる」。頭では理解している。だが、Aさんの不安そうな瞳を見ると、どうしても強く言えず、「大丈夫だよ、次から気をつけようね」と優しく声をかけてしまう。そのたびに、指導が甘いと上司から遠回しに指摘される。「美咲さん、もう少し厳しさも必要よ」。そんな言葉が、美咲の胸に深く刺さった。
「私が甘いから、Aさんも成長できないんじゃないか…」
「でも、私が新人だった頃、先輩にきつく言われてどれだけ委縮したか…」
心の声が、美咲の頭の中でぐるぐると渦巻く。日中の業務は、Aさんのフォローと自分の受け持ち患者のケアで常に手一杯だ。記録を終える頃には、とっくに定時を過ぎている。疲れ果てた体で家路につく途中、ふと目にした街灯の光が、やけに寂しく感じられた。
「もう、何も考えたくない…」
さらに追い打ちをかけたのが、委員会の仕事だった。病棟の業務だけでも限界なのに、毎月の会議資料作成、イベント企画。休日も、頭の片隅には常に委員会のことがあった。「なぜ私ばかり…」という思いが募るが、口に出すことはできない。「みんな頑張っているんだから、私も頑張らなきゃ」。そう自分に言い聞かせる毎日だった。同僚たちの忙しそうな背中を見るたびに、「私だけが大変だなんて言えない」と口を閉ざした。
ある夜、美咲は眠れないまま天井を見上げていた。「辞めたい」。その言葉が、初めてはっきりと美咲の心をよぎった。しかし、次の瞬間、別の声が頭の中に響く。「私が辞めたら、Aさんのプリセプターは誰がやるの?」「ただでさえ人手不足なのに、私が抜けたら周りに迷惑がかかる」。その罪悪感が、美咲の心をぎゅっと締め付けた。まるで、見えない鎖でがんじがらめにされているかのようだった。
「もうダメかもしれない…」
「こんなに苦しいのに、どうして私は辞めることすらできないんだろう…」
「なぜ私だけが、こんなに板挟みになって苦しんでいるんだろう…」
「私の存在が、みんなの負担になっているんじゃないか…」
食欲は落ち、好きなはずの食事も砂を噛むようだ。休日はベッドから起き上がることすら億劫になった。友人の誘いも断り続け、いつしか孤独感が美咲を包み込んでいた。鏡に映る自分の顔は、生気を失い、まるで別人のようだった。このままでは、心も体も本当に壊れてしまう。そんな予感が、美咲の胸を深くえぐった。しかし、それでも「辞める」という選択肢は、美咲の中で「迷惑をかける行為」として、固く閉ざされた扉の向こうにあった。その扉を開ける勇気が、美咲にはどうしても見つからなかったのだ。誰かのためにと頑張り続けた結果、自分自身が深く傷つき、出口の見えない迷路に迷い込んでいる。そんな現実に、美咲は静かに絶望していた。